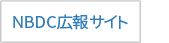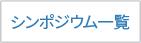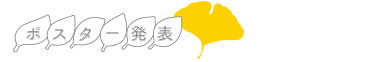
ポスター発表日程
 ポスター発表は以下の日程で行います。
ポスター発表は以下の日程で行います。
【10月5日(水)】
ライトニングトーク① 奇数番号 14:35 ~ 15:10
ポスター発表① 奇数番号 15:10 ~ 16:30
【10月6日(木)】
ライトニングトーク② 偶数番号 13:10 ~ 13:45
ポスター発表② 偶数番号 13:45 ~ 15:05
ご覧ください。
※ポスターや発表スライド等の著作権は、別途記載がない限り発表者・発表者の所属機関に
帰属します。
ポスター・スライド内の図や文言を転用する際には、著作者と話し合っていただくよう
お願いいたします。
ポスター発表詳細(ポスター情報)
| 番 号 | 1 |
|---|---|
| タイトル | DDBJ |
| 発表者 | 〇中村保一、神沼英里、小笠原理、有田正規、大久保公策、高木利久 |
| 所 属 | 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 DDBJ センター |
| 要 旨 | DDBJ (http://www.ddbj.nig.ac.jp) は米国 NCBI, 欧州EBIとの国際共同事業である International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC) のパートナーとして、塩基配列 DB ならびにその解析リソースを維持するとともに、遺伝研スーパーコンピュータの運営を担当し、データアーカイブとその解析系の提供を行っている。INSDC では伝統的な配列 DB (Traditional INSDC DB) の他、新型シーケンサ由来データ DB の DDBJ Sequence Read Archive (DRA) や、研究プロジェクトに関する BioProject DB、サンプルに関する BioSample DB、ヒトの表現型/遺伝子型 DB である Japanese Genotype-phenotype Archive (JGA) をNBDCと共同で運営している。諸事情から開発が停止していたオミックス DB の立ち上げ状況など、DDBJ の運営についての進捗と展望・諸問題について報告する。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 3 |
|---|---|
| タイトル | NGS技術の進展と登録データ |
| 発表者 | ○仲里猛留、大田達郎、坊農秀雅 |
| 所 属 | 情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター |
| 要 旨 | 超並列シーケンサ(NGS)は今や生命科学分野で必要不可欠な技術となっており、その公共データベースであるSequence Read Archive (SRA) も登場から10年近くが経過した現在は3500兆塩基対(≒3.5PB)のデータを収載するまでに成長した。DBCLSではこのような大規模データの取扱いに早くから注目し、効率良い再利用のために目次サイトであるDBCLS SRA (http://sra.dbcls.jp/)の構築・運用を行ってきた。DBCLS SRAでは、目的や機器、生物種別に登録データを検索することが可能である。加えて疾患からの検索、非モデル生物種データの検索機能も充実させた。また、2010年より登録件数の推移を統計情報として公開しており、NGS機器の栄枯盛衰を垣間見ることができる。最近は、遺伝子発現データがGEOにも登録されるなど、他のデータベースにもまたがる登録が増えており、それらを横断的に検索するためDDBJと協力してプロジェクトやサンプルのデータベースであるBioProjectやBioSampleとの連携を進めている。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 4 |
|---|---|
| タイトル | GGGenome & CRISPRdirect:ゲノム編集のオフターゲット効果を防ぐための塩基配列検索ツール |
| 発表者 | 〇内藤雄樹、坊農秀雅 |
| 所 属 | 情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター |
| 要 旨 | CRISPR/Cas9ゲノム編集法は、ゲノムの任意の部位を編集することのできる技術として近年急速に普及している。しかし、標的以外の部位に意図せずゲノム編集が起こってしまうオフターゲット効果を防ぐことや、塩基配列のノックインなど標的配列に制約のあるゲノム編集を行うためのガイドRNA設計は必ずしも容易でない。そのようなガイドRNA設計を支援するウェブツールとして、我々が公開している高速塩基配列検索GGGenome (http://GGGenome.dbcls.jp/) および、CRISPR/Cas9ゲノム編集法のためのガイドRNA設計ソフトウェアCRISPRdirect (http://crispr.dbcls.jp/) を紹介する。本年のアップデートでは、ゲノムが公開されている200種類以上の生物種に対応したほか、近年のCRISPR/Cas9法の改良をふまえ、NGG以外のPAM配列を認識するCas9のためのガイドRNA設計も簡便に行えるようにした。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 7 |
|---|---|
| タイトル | 生命科学系データベースアーカイブ・IntegbioデータベースカタログのUPDATEとデータベース内項目調査 |
| 発表者 | ○八塚茂1)、信定知江1)、大久保克彦2)、井上圭介3)、加藤健弘2)、宮崎敦子1)、畠中秀樹1) |
| 所 属 | 1)科学技術振興機構 バイオサイエンスデータベースセンター 2)株式会社日立製作所 3)株式会社日立公共システム |
| 要 旨 | 生命科学系データベースアーカイブ (http://dbarchive.biosciencedbc.jp/) は、国内で産生された生命科学のデータをダウンロード可能な形で長期間維持するサービスであり、115 件を超えるデータベース(DB)が登録されている。2016年においては以下のUPDATEを行った。 ・データベース/データメタデータの詳細検索機能を追加 ・データベース/データメタデータのエクスポート機能を追加 ・全てのデータベース/データにDOI(Digital Object Identifier)を付与 ・データベースメタデータにおいて、研究者情報(ORCID, researchmap)・文献情報(pubmed, J-GLOBAL)・プロジェクト情報(生命科学系主要プロジェクト一覧、J-GLOBAL)へのリンクを付与 Integbioデータベースカタログ (http://integbio.jp/dbcatalog) は文科省・厚労省・農水省・経産省の連携のもと主に国内の生命科学系DBの所在と概要を提供するサービスとして始まり、現在国内外の生命科学系DB情報約1570件を集積している。新たにデータの一括ダウンロードサイト情報と統合TVへのリンクを付加し、国外DB情報収集への注力など内容の充実も図っている。また、本カタログに収録されたDB情報を元にDB内のデータ項目調査を行った。これは目的データを含むDBの探索がより容易になるだけでなく、DB統合化における基礎情報となることが期待される。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 17 |
|---|---|
| タイトル | セマンティック・ウェブ技術を用いたCyanoBase更新系の整備 |
| 発表者 | ○藤澤貴智、中村保一 |
| 所 属 | 情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 |
| 要 旨 | CyanoBase (http://genome.microbedb.jp/cyanobase/) は、1996年、かずさDNA研究所において開発され、その後、ラン藻を中心とする光合成関連微生物のゲノムスケールのデータ追加・更新が手動によりデータ拡張されてきた。また、データベースへの機能追加およびシアノバクテリア研究者によって提供された遺伝子破壊株情報およびキュレーターによってラン藻遺伝子に関する文献リファレンス情報が集積され、主に遺伝子に関連するアノテーションデータが拡張されてきたが、2011年7月、国立遺伝学研究所への移管後、ゲノムエントリー追加が未対応な状況であった。 CyanoBase20周年を迎える2016年において、ゲノムエントリー追加についてデータ変換・投入の更新系を整備することにより、ドラフトゲノムを含む374のゲノム情報を追加・拡充した。本発表においては、シアノバクテリアゲノムプロジェクトの取得などセマンティック・ウェブ技術の利用を中心に発表する。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 18 |
|---|---|
| タイトル | 微生物統合データベースMicrobeDB.jp 2.0 |
| 発表者 | ○森宙史1)、藤澤貴智1)、千葉啓和3)、鈴木真也2)、山本希2)、内山郁夫3)、菅原秀明1)、中村保一1)、黒川顕1),2)、MicrobeDB.jpプロジェクトチーム1),2),3) |
| 所 属 | 1)情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 2)東京工業大学 生命理工学院 3)自然科学研究機構 基礎生物学研究所 |
| 要 旨 | 微生物は発酵や抗生物質生産、感染症など様々な人間活動に深く関わっているため研究の歴史も古く、蓄積されたデータや知識は膨大かつ多様である。さらにゲノムやメタゲノムなどの大規模データも多数産出されているため、これらを横断的かつ簡便に利用出来れば、新たな仮説の創出がより容易になると期待できる。我々は、国内外に散在する細菌の各種オミックス情報を広く収集し、遺伝子、ゲノム、環境の3つの軸に沿って様々な知識を整理し、ゲノム情報を核としてセマンティックウェブ技術により統合した統合データベース「MicrobeDB.jp」をこれまで開発してきた。本発表では、ゲノムやメタゲノム等のデータを大幅に追加すると同時に種々のオントロジーを更新し、統合DBを用いた様々な解析結果を提示するアプリケーション群やユーザナビゲーションシステムによって、超高度化されたMicrobeDB.jp 2.0の詳細について、発表する。MicrobeDB.jpのWebサイト: http://microbedb.jp/MDB/ |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 20 |
|---|---|
| タイトル | 植物ゲノム情報活用のための統合研究基盤の構築 |
| 発表者 | ○柴谷多恵子1)、市原寿子1)、白澤沙知子1)、中村保一1)、中谷明弘2)、浅水恵理香3)、平川英樹1)、田畑哲之1) |
| 所 属 | 1)かずさDNA研究所 2)大阪大学大学院 医学系研究科 3)龍谷大学 農学部 |
| 要 旨 | 我々は、国内外に散在する多様な植物ゲノム関連情報を集約・整備した情報基盤として、ポータルサイトPlant Genome DataBase Japan (PGDBj、http://pgdbj.jp) を提供している。PGDBjのDBの内、リソースDBでは、理化学研究所BRCが開発した植物遺伝子の串刺し検索システムSABRE2 (http://sabre.epd.brc.riken.jp/SABRE2.html) を拡充し、BRCおよびNBRPに由来する情報とPGDBjで整備した情報、計17植物種の約220万件を対象とした横断検索システムを公開している。また、DNAマーカーDBでは、62植物種の約20万件のマーカー情報、42植物種の約6800件のQTL情報を公開している。整備したこれらの情報の実用化利用の足掛かりとして、育種に特化したDNAマーカーの検索システムも新たに構築し、公開した。現在、各DBエントリーをRDF化し、その構造に基づく横断検索システム及びゲノムブラウザJBrowseを介して検索結果を提示するシステムの構築を進めており、これらの情報のさらなる有効利用を実現する基盤を提供する予定である。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 21 |
|---|---|
| タイトル | 遺伝子オルソログDBによる植物ゲノムDBの統合 |
| 発表者 | ○中谷明弘1)、市原寿子2)、柴谷多恵子2)、白澤沙知子2)、中村保一2)、浅水恵理香3)、平川英樹2)、田畑哲之2) |
| 所 属 | 1)大阪大学大学院 医学系研究科 2)かずさDNA研究所 3)龍谷大学 農学部 |
| 要 旨 | 配列の類似したアミノ酸配列(遺伝子)の種間の対応関係をオルソログと定義し、緑色植物とラン藻のオルソログ情報をPGDBjオルソログDB (Plant Genome DataBase Japan, Ortholog Database;http://pgdbj.jp/od3/) として公開しています。遺伝子の名前や染色体上での位置の他に機能注釈中のキーワードや配列自体をクエリとした検索が可能になっています。また、オルソログ関係にある遺伝子の並び順を生物種間で保存している染色体領域(シンテニー様領域)の情報を用いて、遺伝子やDNAマーカーの生物種横断的な対応関係の推定や探索も可能になっています。これまでに、NCBI RefSeq (Release 75)から取得した緑色植物のアミノ酸配列(64種・約230万配列)とラン藻のアミノ酸配列(231種・約86万配列)を対象として、両系統群内での全アミノ酸配列間のBLASTによる配列相同性の算出、および、それに基づいた全アミノ酸配列の分類を行い、オルソログ情報の生成およびデータベース化を完了しています。計算機処理用データのダウンロードも可能になっています。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 22 |
|---|---|
| タイトル | 作物品種情報に対するセマンティックウェブ技術の適用 |
| 発表者 | ○市原寿子1)、藤井浩2)、櫛田達矢3)、田畑哲之1) |
| 所 属 | 1)かずさDNA研究所 2)農研機構 果樹茶業研究部門 3)科学技術振興機構 バイオサイエンスデータベースセンター |
| 要 旨 | 「植物ゲノム情報活用のための統合研究基盤の構築」では、従来のウェブ技術に加え、セマンティックウェブ技術(以下SWT)を用いた植物関連情報の統合を試みており、ゲノム関連情報を対象の中心としたデータベース統合の他、作物品種の形質情報へSWTを適用したシステム構築を実施している。本発表では、農林水産省品種登録ホームページ (http://www.hinsyu.maff.go.jp/) から公開されている情報を用いて、「作物品種の系統情報」や「有用農業形質の品種間での比較や分離に関わる情報」の検索を効率化するシステムの構築について報告する。このシステムではSWTによりリンクした多様な情報に基づき、多数の条件を複雑に組み合わせた検索が可能となり、「品種名」から「その品種が保有する農業形質」の情報、または「農業形質名」から「品種」や「系統」に関わる情報を抽出することができる。例えば検証した作物のうち、リンゴにおいては、種子親を‘ふじ’とする多数の品種の果汁糖度の情報の一括抽出や、品種‘夏緑’の情報から、種子親である‘きたかみ’の更にその種子親として、品種名‘東北2号'の自動抽出に成功した。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 23 |
|---|---|
| タイトル | RDFを利用して実験動物の表現型と疾患との関連性を示すシステム |
| 発表者 | 熊谷禎洋1)、高月照江2)、斎藤実香子2)、高山英紀2)、○桝屋啓志2) |
| 所 属 | 1)株式会社日立製作所 医療情報ソリューション部 2)理化学研究所 バイオリソースセンター |
| 要 旨 | 疾患の原因解明や治療法開発において、動物モデルは極めて重要な役割を果たしている。例えば、遺伝子の関与が大きいと言われる希少疾患の原因解明では、変異動物が示す表現型と原因遺伝子の情報の貢献が大きい。疾患研究の現場において、より多くの実験動物の情報、特に表現型データが提供されることが求められている。 統合化推進プログラム「生命と環境のフェノーム統合データベース」では、国内のデータベースより表現型データを収集し、Resource Description Framework (RDF)の技術を用いて統合化し、ポータルサイト、J-Phenome (http://jphenome.jp) をより利用できるようにしている。我々は、J-phenomeのデータと、複数の生物の表現型の同等性を示すUberPhenoオントロジーを用いて、RDF化した表現型データ間の同等性、及び疾患との関連を示すためのアプリケーションを試作したので紹介する。疾患名、表現型、器官組織名の入力から、研究分野の語彙の違いを超えて対応する疾患モデル動物の検索が可能である。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 24 |
|---|---|
| タイトル | 生物種横断的な表現型データポータルサイトJ-phenomeについて |
| 発表者 | ○高月照江1)、斎藤実香子1)、高山英紀1)、大島和也1)、田中信彦1)、熊谷禎洋2)、桝屋啓志1) |
| 所 属 | 1)理化学研究所 バイオリソースセンター 2)株式会社日立製作所 医療情報ソリューション部 |
| 要 旨 | 我々は、遺伝子の多様性の結果として現れる生物の表現型情報を、モデル動物(マウス、ラット、ゼブラフィッシュ、メダカ)、ゲノム編集研究など、幅広い研究コミュニティから収集し、公開する目的で表現型ポータルサイトJ-phenome (http://jphenome.info/) を作成した。 各研究コミュニティで表現型を扱うデータベースからデータ提供を受け、提供元のデータベース単位で、個別の二次的なメタデータのデータベースとして管理を行っている。全ての表現型データは、各分野で標準的に使われている表現型のオントロジーを用いてアノテーションを行ない、統一したスキーマでRDF形式にすることで、個別DBでありながら、すべてのデータを横断的に検索できるようにした。また、MicrobeDB (http://mdb.bio.titech.ac.jp/) 、及びMornarch Initiative (https://monarchinitiative.org/) とのデータ連携も可能となり、従来より情報を広く流通させることができる見込みである。 現在J-phenomeでは、マウス(約6000系統)、細胞(約3800株)、微生物(約15000系統)、ラット(170系統)メダカ(298系統)を公開し、全て自由にダウンロード可能である。我々は、J-phnomeから発信される表現型情報の利用を通して、各種実験動物の疾患研究への利用を始め、幅広い研究への貢献を目指している。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 25 |
|---|---|
| タイトル | 理研メタデータベースの運用とデータ統合の実際 |
| 発表者 | ○戀津魁1)、桝屋啓志1),2)、小林紀郎1),2),3) |
| 所 属 | 1)理化学研究所 情報基盤センター 2)理化学研究所 バイオリソースセンター 3)理化学研究所 ライフサイエンス技術基盤研究センター |
| 要 旨 | 理化学研究所は物理、化学、ライフサイエンスをはじめとするサイエンスの総合研究所であり、多種多様な研究データを産出している。これらのデータを公開するために、理研メタデータベース (http://metadb.riken.jp/) を構築し、公開インフラとして利用している。 理研メタデータベースは、メタデータ公開の標準仕様であるResource Description Framework (RDF)に準拠して設計されており、複数のデータベースを統合、公開することができる。一つのデータベースは1つのRDF Graphとして管理され、更にデータレコード(RDFリソース)はすべてクラス概念を付してまとめ上げることで、ライフサイエンス分野でよく使われている互いに関連するテーブル形式のデータ構造を持たせ、表示することができる。RDFの特性を活用し、従来のテーブルデータとは異なり、異なるデータベースのデータも統合しつつテーブルの上に表示することが可能となっている。 理研メタデータベースはSPARQLエンドポイント機能も備わっており、ユーザーはテーブル形式で表示されるデータ構造を参考にしながらSPARQLクエリを記述し、より詳細なデータ解析を行うことができる。 2016年7月現在、センター横断的に110個のデータベースが統合され、クラス数2119、トリプル数152784620に及ぶデータを公開している。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 27 |
|---|---|
| タイトル | SSBD:生命動態情報と細胞・発生画像情報の統合データベース開発の進展 |
| 発表者 | ○遠里由佳子、ホー・ケネス、京田耕司、大浪修一 |
| 所 属 | 理化学研究所 生命システム研究センター 発生動態研究チーム |
| 要 旨 | 画像処理を伴う生細胞イメージングや、シミュレーションを伴うモデリングの結果として、分子や細胞、個体などの生命現象の時空間情報を数値として含む定量データが産出されている。しかし、それらのデータは、インターネット上に散在しており、データの再利用を促進する上で、その集約化が課題となっていた。そこで我々は、定量データを格納・共有する、生命動態システム科学の統合データベースSSBD (Systems Science of Biological Dynamics database; http://ssbd.qbic.riken.jp) を構築した(Tohsato et al. Bioinformatics, accepted)。さらに2015年4月より、定量化が求められる画像データの格納と共有も開始している。SSBDの定量データや画像データのメタ情報は、RDF形式で RIKEN メタデータベースや NBDC RDFポータルに共有されており、SPARQLにより複数のデータベースを横断的に検索できる。本ポスターでは、それら生命動態情報と細胞・発生画像情報に関するデータベース開発の進展を報告する。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 29 |
|---|---|
| タイトル | SSBD:生命動態情報と細胞・発生画像情報を活用するソフトウェアの開発とその進展 |
| 発表者 | ○ホー・ケネス、遠里由佳子、京田耕司、大浪修一 |
| 所 属 | 理化学研究所 生命システム研究センター 発生動態研究チーム |
| 要 旨 | 生命動態システム科学の統合データベースSSBD (Systems Science of Biological Dynamics database; http://ssbd.qbic.riken.jp) では、バイオイメージインフォマティクス技術や計算機シミュレーションにより得られる分子や細胞、個体などの多様な生命現象の時空間動態に関する定量データや画像データを、データベースに格納・共有している(Tohsato et al. Bioinformatics, accepted)。本年度は、それらデータの可視化や解析に利用できるREST APIなどのウェブサービスをはじめ、さまざまなソフトウェアツールやプラットフォームの開発・改善を行い、SSBDで公開した。また、SSBDのオープンソース版の開発も行い、ソースをGitHubで、イメージをDocker Hubで公開した。これらすべてのソフトウェアは、GPLv3で配布されている。本ポスターでは、SSBDで提供しているサービスおよびソフトウェアツール開発の進展を、その活用例を含めて紹介する。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 34 |
|---|---|
| タイトル | GlyTouCan Partner:糖鎖データ連携のためのプログラム |
| 発表者 | ○山田一作1)、松原正陽1)、新町大輔2)、青木ポール信行2)、木下聖子2),3)、成松久3) |
| 所 属 | 1)野口研究所 2)創価大学 理工学部 3)産業技術総合研究所 糖鎖技術研究グループ |
| 要 旨 | 糖鎖は分岐を含む複雑な化学構造であり、糖鎖研究では単糖の種類や結合位置が不明などの曖昧さを含む構造も利用される。我々は糖鎖構造を明確にするため、新しい糖鎖構造表記法であるWURCS(PMID: 24897372)やGlyTouCan (国際糖鎖構造リポジトリ: https://glytoucan.org PMID: 26476458) を開発してきた。GlyTouCanは糖鎖構造に対してアクセッション番号を付与するとともに、糖鎖構造ハブとして様々なデータベースとの連携を進めている。このようなデータベース連携のためのデータはGlyTouCan Partnerから提供される。GlyTouCan Partnerの一つであるGlycoNAVI (http://glyconavi.org) は、PDB(PMID: 14634627)やPubChem(PMID: 26400175)などの化学構造とGlyTouCanの糖鎖構造を橋渡しするデータをWURCSを利用することで提供している。本発表ではGlyTouCan PartnerによるGlyTouCanの利活用と糖鎖データの統合化について紹介する。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 37 |
|---|---|
| タイトル | 日本糖鎖科学コンソーシアムデータベース (JCGGDB) |
| 発表者 | ○ソロビヨワ・イェレナ1)、藤田典昭1)、鹿内俊秀1)、鈴木芳典1)、木下聖子1),2)、成松久1) |
| 所 属 | 1)産業技術総合研究所 糖鎖技術研究グループ 2)創価大学 理工学部 |
| 要 旨 | 産総研・糖鎖技術研究グループは文部科学省委託研究開発事業やJST/NBDCの「ライフサイエンスデータベース統合化推進プログラム」に参加し、糖鎖関連の多種多様なデータベースを構築し、糖鎖関連データベースの統合化を推進してきた。2010年から公開されている糖鎖科学コンソーシアムのデータベース(JCGGDB; http://jcggdb.jp)を活用している。我々は、糖鎖関連データベースの統合化の活動において、それらのデータベースのコンテンツをRDF化するとともに、オントロジーの開発も行っている。RDF化とオントロジーの開発にあたっては、SKOS、OWL、RDFなどのセマンティックWeb技術を用いることより、関連データベース及びオントロジーとの連結を可能にする。糖鎖関連データベースに蓄積されている情報の理解をより深めるために、データの検索や階層構造の閲覧、詳細表示ができるユーザインタフェースも開発と提供を行っている。現在、RDFの形式で公開されているデータベースはGlycoProtDB (http://acgg.asia/db/gpdb) 、LfDB (http://acgg.asia/db/lfdb) 、GGDB (http://acgg.asia/db/ggdb) 、GDGDB (http://acgg.asia/db/diseases/gdgdb) 、PACDB (http://acgg.asia/db/diseases/pacdb) である。実験で得られた糖鎖修飾位置のグライコフォームの情報も公開した。RDF化された情報は糖鎖関連の分野で研究する研究者の知識の理解と整理を容易いものとし、セマンティックウェブ化した様々なデータと結びつくことで新しい知識発見に役立つと考えられる。このような糖鎖関連データベースの統合化について報告する。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 39 |
|---|---|
| タイトル | 蛋白質複合体データベース:OLIGAMI |
| 発表者 | ○藤原和夫、池口雅道 |
| 所 属 | 創価大学 理工学部 共生創造理工学科 |
| 要 旨 | OLIGAMI(OLIGomer Architecture and Molecular Interface)は、ドメインのフォールド分類(SCOPe)と複合体情報の2軸を持ち、注目している蛋白質の複合体構造を素早く探し、視覚化することができるデータベースとして公開してきた。OLIGAMIでは複合体情報として、生物学的複合体の座標データ(Biological assembly)に含まれる分子鎖の種類がポリペプチド鎖か核酸鎖か、アミノ酸配列が同じか異なっているかといった情報をアルファベットで表したChain Formulaを提供している。今回の発表では、以下に示す6つのポイントについて行った改良点について紹介する。1)複合体インターフェースの二次構造分析、2)分子間βシート、分子間SS結合情報の追加、3)立体構造ベースでのChain Formulaの提供、4)詳細検索機能、5)フォールド分類へのCATH分類の追加、6)膜蛋白質データベースOPM情報の追加による水溶性蛋白質、膜蛋白質の選択機能。 URL http://protein.t.soka.ac.jp/oligami/ |
| 番 号 | 43 |
|---|---|
| タイトル | jPOST: 今こんな感じです |
| 発表者 | ○守屋勇樹1)、河野信1)、奥田修二郎2)、山本格3)、松本雅記4)、小林大樹5)、荒木令江5)、吉沢明康6)、五斗進6)、 田畑剛7)、杉山直幸7)、石濱泰7) |
| 所 属 | 1)情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター 2)新潟大学大学院 医歯学総合研究科 3)新潟大学 産学地域連携推進機構 4)九州大学 生体防御医学研究所 5)熊本大学大学院 生命科学研究部 6)京都大学 化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 7)京都大学大学院 薬学研究科 |
| 要 旨 | 異なる実験由来のプロテオームデータを統合し、統一された信頼基準で結果を解釈するために、jPOST(Japan ProteOme STandard Repository/Database, http://jpost.org/)では、質量分析装置から出力される生データを含む、プロテオームデータを投稿・蓄積するためのリポジトリ、生データを再解析するための標準化されたワークフロー、再解析後の高品質なプロテオームデータを蓄積・可視化するデータベースの3つを開発している。リポジトリは今年5月に一般公開され、現在プロテオームデータが蓄積されつつある。再解析ワークフローにおいては、複数のピーク検出ソフトとサーチエンジンを組み合わせることで、生データから高精度かつより多くのペプチドやタンパク質を検出する手法を開発している。またデータベースは、すでにRDF化が進んでいる他の生命科学データベースとの相互利用を考慮し、RDF技術を基に開発を進めており、ProteomeCentralと共通のメタデータを表現するためのRDFスキーマ及び、ペプチドやタンパク質の同定結果を記述するためのRDFスキーマのデザインが進んでいる。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 45 |
|---|---|
| タイトル | jPOST: 再解析考え中です |
| 発表者 | ○吉沢明康1)、田畑剛2)、守屋勇樹3)、河野信3)、奥田修二郎4)、渡辺由4)、山本格5)、松本雅記6)、高見知代6)、 小林大樹7)、荒木令江7)、杉山直幸2)、五斗進1)、石濱泰2) |
| 所 属 | 1)京都大学 化学研究所 バイオインフォマティクスセンター 2)京都大学大学院 薬学研究科 3)情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター 4)新潟大学大学院 医歯学総合研究科 5)新潟大学 生体液バイオマーカーセンター 6)九州大学 生体防御医学研究所 7)熊本大学大学院 生命科学研究部 |
| 要 旨 | 2015年から統合化推進プログラムのもとで構築が開始されたプロテオーム統合データベース『jPOST』 (http://jpost.org/) は、実験で得られた質量スペクトルの生データを公開するためのリポジトリと、そのデータを独自に解析(再解析)した結果を収録するデータベースから構成される。この「再解析」のために、「曖昧なデータ、“グレー”なデータをデータベース検索の結果から極力取り除く」方法論を、現在構築中である。この過程で、「b-ion系列・y-ion系列のイオンが、連続したアミノ酸残基にアサインされているか」など、人手による質量ピークとアミノ酸配列の比較と等価の作業によって同定結果を検証したところ、ピーク探知やデータベース検索に用いるソフトウェアによって、探知し易いイオンやアミノ酸配列に相違があることが判明した。これは実装されているアルゴリズムの差異に起因すると考えられ、この特徴を利用することで、同定過程に於ける“取りこぼし”を減少させることが可能であると考えられる。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 48 |
|---|---|
| タイトル | ヒトマルチオミクスデータのRDF化と横断検索 |
| 発表者 | ○河野信1)、若栗浩幸2)、田中聡3)、鈴木穣4)、菅野純夫4) |
| 所 属 | 1)情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター 2)株式会社ダイナコム 3)Trans-IT 4)東京大学大学院 新領域創成科学研究科 |
| 要 旨 | シーケンス技術の発展にともなって、ゲノム配列だけでなく遺伝子発現やDNAメチル化、転写開始点など、同一のサンプルからさまざまな種類のオミクスデータが測定可能になった。これまでこれらのデータを扱う際は、オミクスデータごとに個別に解析されるか興味の対象となっている特定の部位を横断的にゲノムブラウザで表示するなどに限られ、種類の異なるオミクスデータを網羅的に取り扱うことは難しかった。今回、これらのデータを統一的に表現するためにKERO(Kashiwa Encyclopedia of Regulatory Omics)データベース[1]に収録されているChIP-seq・BS-seq・TSS-seq・RNA-seqのデータをRDF化した。すでにRDF化されているEnsemblのゲノムアノテーションと組み合わせ、FALDO[2]で表現されたゲノム座標を軸として種類の異なるオミクスデータを横断的かつ網羅的に検索する仕組みを構築したので報告する。 [1] http://kero.hgc.jp/ [2] Bolleman et al., J Biomed Semantics, 7:39 (2016) |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 49 |
|---|---|
| タイトル | 疾患ヒトゲノム変異の生物学的機能注釈を目指した多階層オミクスデータの統合 Regulatory Omics Database for Analyzing Transcriptional Consequences of Human SNVs |
| 発表者 | 入江拓磨1)、○鈴木穣1)、河野信3)、土原一哉2)、菅野純夫1) |
| 所 属 | 1)東京大学大学院 新領域創成科学研究科 メディカル情報生命 2)国立がん研究センター 先端医療開発センター 3)情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター |
| 要 旨 | 演者らはヒトゲノム多型・変異に生物学的機能注釈を与えるべく、ゲノム変異位置、近傍のエピゲノム(ヒストン修飾、DNAメチル化パターン)、トランスクリプトーム情報(発現量、スプライスパターン)をヒトゲノム情報に統合したデータベースの構築を行っている。現在、データの統合はがんゲノム解析を志向したものを中心に行っているが、最終的には疾患の別を超えたデータの統合を目指す。特に本データベースでは、培養細胞系あるいは生物種を超えてマウスをはじめとする動物モデル系から得られたオミクスデータに焦点を当てている。これにより臨床検体で集積が乏しいエピゲノム情報を充実させ、同時に生物学的機能解析の実践の場としてのモデル系におけるオミクス情報を整備する。我々はこれまでに、がん細胞培養細胞株をモデル系にしたデータベースの構築と公開を行っている。26種類の細胞株について、それぞれ全ゲノムシークエンス、遺伝子発現情報、エピゲノム情報(8種類のヒストン修飾とDNAメチル化情報)を統合したものである。また、本データベースでは外部参照データとして、国内外の日本人ゲノム解析プロジェクトにより産出された日本人多型データ約5000人分が無償、自由に閲覧可能となっている (http://kero.hgc.jp/) 。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 51 |
|---|---|
| タイトル | 統合化推進プログラムにおけるヒトゲノムバリエーションデータベース |
| 発表者 | ○澤井裕美1)、小池麻子2)、豊田裕美1)、山崎茉莉亜1)、井ノ上逸朗3)、辻省次4)、徳永勝士1) |
| 所 属 | 1)東京大学大学院 医学系研究科 2)日立製作所 研究開発グループ 3)情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 4)東京大学 医学部附属病院 |
| 要 旨 | SNPタイピング技術と次世代シーケンサ技術の技術革新により、ゲノムワイドな疾患関連多型・変異探索が可能となり、多くの疾患関連多型・変異が発見されつつある。我々のグループでは国内/アジアにおけるこれらのデータの散逸を防ぎ研究者間でデータ共有化するために、2007年よりGWAS-DB, CNV-DBを、2011年度よりHuman variation DB, HLA-DBを構築し (https://gwas.biosciencedbc.jp/) 、GWASデータ、NGS変異データの提供を広く呼びかけると共にデータの預入れと再配布の運用を行ってきた。2014年度からはNBDCがデータの預入れと再配布を実施し、その計算結果の可視化、及び、主要なDBの癌体細胞変異のドライバー変異やシグナルパスウェイとの関係性の可視化を本DBで引続き実施している。これらのDBにおいてはGWASのデータとともに、健常者や患者の多様な生殖細胞変異(SNV、長配列の挿入/欠失、構造多型)を収集対象とし、文献から抽出した疾患関連変異・臨床情報30,000以上のエントリーも登録しており、日本人/アジア人の変異と表現型(疾患、薬剤応答、ウィルス耐性)との関係の体系化を目指している。 |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 60 |
|---|---|
| タイトル | 創薬・疾患研究のための情報体系構築 ~ 基礎研究から臨床試験まで ~ |
| 発表者 | ○坂手龍一1)、深川明子1)、鈴木雅2)、松山晃文1) |
| 所 属 | 1)医薬基盤・健康・栄養研究所 2)日本製薬工業協会 医薬産業政策研究所 |
| 要 旨 | 創薬・疾患研究の推進には、基礎から応用への研究の流れを俯瞰する情報体系が重要である。大学研究者が創薬開発情報を、また、製薬会社研究者が基礎研究情報を容易に取得できれば、適切なターゲット探索などの研究効率が向上すると考えられる。このような情報体系の構築を目指し、我々は①医薬基盤・健康・栄養研究所のデータベース統合検索[1]と、②実験動物・疫学研究・バイオバンクの所在情報データベース[2]の構築を行ってきた。さらに、現在、創薬・疾患研究の対象として注目されている難治性疾患(希少疾患を含む)について、③厚生労働省指定難病306疾病の臨床試験情報の調査[3]を実施しデータベースを構築した。疾患と薬物の情報を横断的に取得可能とすることで、発症機序解明やドラッグリポジショニング標的探索の促進を図る。これらにより、創薬・疾患研究の新規知識発見のためのポータルサイト構築を目指している。 [1] 創薬支援データベース統合検索 https://alldbs.nibiohn.go.jp [2] メディカル・バイオリソース・データベース https://mbrdb.nibiohn.go.jp [3] 「指定難病に対する臨床試験実施状況」 政策研ニュースNo.48 (H28.7) |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 62 |
|---|---|
| タイトル | 統合データウェアハウスTargetMineの高度化とデータ解析ツール |
| 発表者 | ○陳怡安、ロケシュ・テリパチ、川島和、水口賢司 |
| 所 属 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 バイオインフォマティクスプロジェクト |
| 要 旨 | 私たちは国際的に広く使用されている30以上の公共のデータソースを統合し、創薬の初期研究における支援を目的とした統合データウェアハウスTargetMine (http://targetmine.mizuguchilab.org) を開発、公開している。創薬標的の探索のために、TargetMineはデータモデルを常に改良し、新規のデータを追加してきている。最近では、特に医薬品に関する情報に力を入れており、本発表では、薬剤の代謝酵素、別名、解剖治療化学分類(ATC分類)、日本標準商品分類(JSC)などの情報とそれらの統合解析機能を紹介する。さらに、定型的な解析だけでなく、多面的な意思決定を対話的に支援する補助解析ツール(ワークフロー機能)を開発した[1]。これにより、創薬標的の探索のみならず、一般的な創薬支援のデータ解析プラットフォームを提供可能になった。 [1] Chen et al., An integrative data analysis platform for gene set analysis and knowledge discovery in a data warehouse framework. Database, 2016: baw009. |
| 発表資料 | |
| 番 号 | 63 |
|---|---|
| タイトル | 創薬・疾患研究のためのデータベース検索システム Sagace |
| 発表者 | 長尾知生子1)、○五十嵐芳暢2)、森田瑞樹1),3)、陳怡安1)、深川明子4)、坂手龍一5)、水口賢司1) |
| 所 属 | 1)医薬基盤・健康・栄養研究所 バイオインフォマティクスプロジェクト 2)同 トキシコゲノミクス・インフォマティクスプロジェクト 3)岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 クリニカルバイオバンクネットワーキング事業化研究講座 4)医薬基盤・健康・栄養研究所 政策・倫理研究室 5)同 難病資源研究室 |
| 要 旨 | 医薬基盤・健康・栄養研究所では、JSTバイオサイエンスデータベースセンターと連携し、データベース横断検索システムSagace (http://sagace.nibiohn.go.jp) を開発・公開している。 Sagaceは、創薬・疾患に特化した約180のデータベースを選定・分類して検索対象とし、ファセット(データベースの分類)による検索結果の効率的な絞り込みと、メタデータ(データに関する事項を記述したデータ)を反映した効果的な検索結果の表示を実装した検索システムで、一般的な横断検索システムよりも創薬・疾患研究に関する情報を効率的に発見できる。 今年度は、検索対象として追加した治験に関するデータベースに新規メタデータを付与することにより、臨床研究情報に関連する検索を強化した。また、検索エンジンの入れ替えにより、検索結果表示速度が飛躍的に向上した。 Sagaceではこれらの取り組みを通じ、より効率的に創薬・疾患研究を支援する検索システムの構築を目指している。 |
| 発表資料 | |