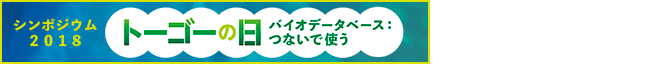- Home
- シンポジウム
- トーゴーの日シンポジウム2018
- ポスター発表 / ワークショップ
2018年度はポスター発表とワークショップを同時開催いたします。
ポスター発表・ワークショップ日程
【ライトニングトーク】 13:40~14:20 未来館ホール
【ポスター発表】 奇数番号 14:20~15:05 偶数番号 15:05~15:50 コンファレンスルーム水星+火星+金星(ひと続きの会場です)
【ワークショップ】 14:40~15:30 コンファレンスルーム水星+火星+金星前ロビー
※ポスターや発表スライド等の著作権は、別途記載がない限り発表者・発表者の所属機関に帰属します。
ポスター・スライド内の図や文言を転用する際には、著作者と話し合っていただくよう お願いいたします。

2018年度初めての試みとして、本シンポジウムのサブテーマ「バイオデータベース:つないで使う」をコンセプトに、NBDC事業で開発しているデータベースを他のデータベースとつなげるとできること、データベースの統合的な利活用について、会場との意見交換を踏まえながら活発な議論が行われることを期待して2題のワークショップを開催いたします。
WS1. ChIP-seqとプロテオーム:公共データをつないで使う:ChIP-Atlas/jPOSTチーム 講演スライド: WS1-1 / WS1-2
種々のプロテオーム情報を標準化・統合・一元管理し、横断的統合プロテオームデータベースを開発することを目的として、jPOSTは2015年に産声を上げた。国際標準リポジトリおよび高精度データ標準化機能を深化させ、より幅広いプロテオームデータの受け皿となる機能を開発しつつある。さらに、他のオミクスとのデータ連携により、シグナル伝達や代謝のネットワーク解析を通じ、生命機能の解明に直接結びつくような解析ツールの提供を目指している。
ChIP-Atlasは、論文などで報告された世界中のChIP-seqデータを収集し、解析したデータを公開している。膨大な量のゲノムータンパク質結合データを収録しており、これらはゲノムブラウザで視覚的に理解できる。すべてのデータには固有のURLがつけられており、ダウンロードやデータ連携が円滑にできる。
本ワークショップでは、ChIP-Atlas とjPOSTが取り組んできたChIP-seqデータとプロテオームデータの連携を例として、他の公共DBとの更なる連携の可能性やそこから生まれるシナジー効果、現状の問題点やユーザー側からのニーズなどについて議論したい。
WS2. 日本人ゲノム多様性統合データベースTogoVarを使ってみる:TogoVar開発チーム 講演スライド: WS2
TogoVar(https://togovar.biosciencedbc.jp/)は、日本人のゲノムバリアントとそれに関係する疾患情報などを収集・整理したデータベース(DB)であり、2018年6月に運用を開始した。主な機能は、各バリアントDBに収録された様々な集団のアレル頻度を比較できることである。様々な人種における頻度情報を持つThe Exome Aggregation Consortium Browser(ExAC)、日本人集団の頻度情報を持つJapanese Multi Omics Reference Panel (jMorp、ToMMo)やHuman Genetic Variation Database(HGVD、京都大学)に加え、NBDCヒトDBに登録・公開されている個人由来ゲノムデータを再解析して集計した頻度情報(JGA-NGSとJGA-SNP)が含まれる。また、バリアントの位置や遺伝子名、アレル頻度、疾患名などによる検索、臨床的意義などによる絞り込みができる。
本WSでは、TogoVarの使い方をデモンストレーションすると共に、今後統合する予定のDBや検索機能を紹介する。エンドユーザーだけでなく、DB開発者からも様々なご意見をいただき、より「使える」「つながる」DBを目指す機会にしたいと考えている。ポスター発表『ゲノム研究に役立つヒトゲノムバリアントデータベース「TogoVar」』もあわせてご覧いただければ幸いである。

優秀ポスター賞決定
本シンポジウムでは、生命科学系データベースの開発者・利用者の活発な研究・開発意欲を奨励するため、優れたポスター発表に対して
「優秀ポスター賞」を授与します。
このたび、参加者の皆様の投票により、トーゴーの日シンポジウム2018「優秀ポスター賞」として、ポスター番号44番「ライフサイエンスデータベースを利活用したバイオインフォマティクス研究」を選出いたしました。受賞者には後日、表彰状をお送りします。
発表者はこちら(発表者へのご案内/PDF:625KB)を ご覧ください。 ライトニングトーク様式/PPT:151KB)
ポスター発表詳細(ポスター情報)
| 番 号 | 1 |
|---|---|
| タイトル | tRNADB-CE:エキスパートがキュレートしたtRNA遺伝子データベース |
| 発表者 | 〇阿部貴志1)、斉藤英司1)、後藤大起1)、池村淑道2)、山田優子1)、武藤昱3)、井口八郎1) |
| 所 属 | 1)新潟大学 2)長浜バイオ大学 3)弘前大学 |
| 要 旨 | tRNA遺伝子の網羅的特徴把握を目標に、公開されている原核生物の6,024の完全長ゲノム、67,053のドラフトゲノム、876のウイルス・ファージ、121の葉緑体、12の真核生物、ならびに221のメタゲノム配列を対象に網羅的な探索を行い、約417万件のtRNA遺伝を公開している(http://trna.ie.niigata-u.ac.jp)。tRNA遺伝子検索を可能な限り完全にするため、3種の予測プログラム(tRNAscan-SE, Aragorn, tRNAfinder)を併用して検索を行い、予測領域が一致しない場合、シニア世代のtRNA研究者がマニュアルにて精査を行い、その判定結果も登録している。ゲノムの登録数の増加に伴い、蓄積したtRNAの精査情報やtRNA研究者のマニュアル精査の際のチェックポイントを組み込んだtRNA判定システムを構築し、更新作業の効率化も図っている。 本DBは世界最大規模の登録件数で、信頼性の高いDBであり、tRNAの分子生物学的な研究や微生物の進化を研究するための新規情報と解析手法を提供している。 Nucleic Acids Res. 2009;37, D163-D168. doi: 10.1093/nar/gkn692 Nucleic Acids Res. 2011;39, D210-D213, doi: 10.093/nar/gkq1007 Front. Genet. 2014;5:114. doi: 10.3389/fgene.2014.00114 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p001 doi:10.18908/togo2018.p001 |
| 番 号 | 4 |
|---|---|
| タイトル | 遺伝子発現解析の基準となるデータを快適に検索できるウェブツールRefEx |
| 発表者 | 〇小野浩雅、坊農秀雅 |
| 所 属 | 情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター |
| 要 旨 | RefEx(Reference Expression dataset; http://refex.dbcls.jp/)は、4つの異なる実験手法(EST、GeneChip、CAGE、RNA-seq)によって得られた40種類の正常組織における遺伝子発現量を並列に表現することで、手法間の比較とともに各遺伝子の発現量を直感的に比較することが可能なリファレンスデータセットである。RefExは、種々のIDや遺伝子名、キーワードで検索できるのはもちろんのこと、任意のIDセットについても複数同時に指定して検索することができ、ある特定の検索結果を指定して得ることが容易である。また、検索結果一覧からユーザが任意で選択した遺伝子について「リスト」に追加・保持する機能を利用することで、それらの詳細情報について一画面で並列に比較することが可能である。現在、FANTOM5 CAGEデータを始めとしたRDF化されている遺伝子発現データセットに対応する遺伝子発現データビューアの開発を進め、ウェブサイト全体のリニューアルを計画している。それらの進捗等をふまえ、開発の方向性について議論したい。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p004 doi:10.18908/togo2018.p004 |
| 番 号 | 5 |
|---|---|
| タイトル | 公共遺伝子発現データベース目次AOEとそれを活用したデータ解析実例 |
| 発表者 | 坊農秀雅 |
| 所 属 | 情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター |
| 要 旨 | ライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS)は、遺伝子発現データベース目次AOE(http://aoe.dbcls.jp/)を開発・維持している。DBCLS SRAのAPIを利用することにより、これまでのEBI ArrayExpressに加えてNCBI Gene Expression Omnibus(GEO)が目次に加わり、より多くのデータが検索可能となった。 ただ検索ツールを作成しただけでは使われにくいため、それらをフル活用したデータ解析研究にも取り組んでいる。演者が長年取り組んできた低酸素刺激による遺伝子発現変動を公共データベースから集めてきてメタ解析を行った研究[1]とその応用事例[2]のほか、昨年の報告以降に公表した3報の共同研究による論文で実際に利用された疾患モデルにおける遺伝子発現データ解析に関しても併せて報告する。 [1] Bono H Biorxiv doi: 10.1101/267310 [2] Nakamura H et al. PLoS One. 2018; 13(2):e0192136. doi: 10.1371/journal.pone.0192136 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p005 doi:10.18908/togo2018.p005 |
| 番 号 | 6 |
|---|---|
| タイトル | NGSデータのエンリッチメント解析による生物学的な解釈 |
| 発表者 | 〇仲里猛留、坊農秀雅 |
| 所 属 | 情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター |
| 要 旨 | 近年、NGS解析が盛んに行われており、ライフサイエンス統合データベースセンター(DBCLS)でも公共NGSデータ検索サービスDBCLS SRAなどを開発してきた。NGS解析というと、マッピングや発現定量などが注目されがちだが、得られた遺伝子リストについて生物学的解釈を行うことも必要不可欠である。DBCLSでは、各遺伝子について疾患や化合物の側面から特徴づけを行うGendooシステムを開発してきた(http://gendoo.dbcls.jp/)[1]。各遺伝子について、関連文献に付与されたMeSH termsを抽出してスコアリングすることにより特徴づけを行っている。従来、生物学的な解釈としてGene Ontologyやパスウェイを用いてのエンリッチメント解析が行われているが、今回、
我々はGendooシステムを拡張し、新たに疾患や化合物の側面からエンリッチメント解析を行えるよう改良を行った。これまでは個々の遺伝子の特徴を並べているにすぎなかったが、本改良により遺伝子リストとしての特徴を示すことが可能となる。 [1] Nucleic Acids Res. 2009;37:W166-9. doi: 10.1093/nar/gkp483. |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p006 doi:10.18908/togo2018.p006 |
| 番 号 | 7 |
|---|---|
| タイトル | GGGenome & CRISPRdirect update:ゲノム編集の実験を支援するためのウェブツール |
| 発表者 | 内藤雄樹 |
| 所 属 | 情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター |
| 要 旨 | CRISPR-Cas9法の実験を支援するためのウェブツールとして、我々が公開している高速塩基配列検索GGGenome (http://GGGenome.dbcls.jp/)およびガイドRNA設計ソフトウェアCRISPRdirect(http://crispr.dbcls.jp/)のアップデートを紹介する。GGGenomeは、20塩基程度の短い配列をゲノム全体から高速に検索することができるツールであり、ミスマッチや挿入・欠失を含む配列であっても検索漏れがなく、ガイドRNAの特異性を確認するために役立つ。CRISPRdirectは、GGGenomeによる検索機能を利用することにより、特異性の高いガイドRNAを簡便に設計できるツールである。昨年以降のアップデートでは、各種の実験動植物や作物などのゲノムを追加したほか、GGGenome APIから取得できる情報を拡充するなど、利用者の要望をもとに改良を行なった。GGGenomeおよびCRISPRdirectは商用利用を含め誰でも無償で自由に利用でき、他のデータベースやソフトウェアとも容易に連携できる。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p007 doi:10.18908/togo2018.p007 |
| 番 号 | 12 |
|---|---|
| タイトル | NBDC RDFポータル |
| 発表者 | 〇川島秀一1)、片山俊明1)、畠中秀樹2) |
| 所 属 | 1)情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター 2)科学技術振興機構 バイオサイエンスデータベースセンター |
| 要 旨 | NBDC RDFポータル(https://integbio.jp/rdf/)の現状について報告する。2015年11月の運用開始時には、10データセット、60億トリプルのデータサイズであったが、2018年7月現在、21データセット、152億トリプルと、2.5倍以上のデータ量に成長しており、さらに複数のデータセットの登録も控えている。そのため単一のVirtuosoインスタンスで運用することができず、大きなデータセット(現状ではDDBJとKEROの2つ)については、別のインスタンスをたてて運用している。本年度より、SPARQLエンドポイントのフロントエンドに、ジョブスケジューリングや、キャッシュによる応答性能向上を行うために、SPARQL proxyを設置している。また、RDFポータルガイドラインも継続的に整備しており、最近では、文献の参照や単位付き値の記述方法などについて、全データセットについて見直しを行った。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p012 doi:10.18908/togo2018.p012 |
| 番 号 | 15 |
|---|---|
| タイトル | 生物学的概念オントロジー由来のナレッジグラフを用いた疾患関連因子の推論 |
| 発表者 | 〇櫛田達矢1)、建石由佳1)、川村隆浩2)、古崎晃司3) |
| 所 属 | 1)科学技術振興機構 バイオサイエンスデータベースセンター 2)電気通信大学 3)大阪大学 産業科学研究所 |
| 要 旨 | 生物学的概念オントロジー(http://purl.bioontology.org/ontology/IOBC)から構築したナレッジグラフを使い、疾患関連遺伝子および化合物の推論を行った。生物学的概念オントロジーをトリプルストアに格納、SPARQLを実行し、線維素溶解(血栓が分解する現象)から3ステップ以内で繋がる概念の集合のデータを獲得、このデータをCytoscapeを使ってグラフとして可視化し、これを線維素溶解ナレッジグラフと呼んだ。線維素溶解ナレッジグラフでは、「ある疾患(例、血小板凝集)に対して、それに先行して生起する生命現象(例、血栓塞栓症)」や「その生命現象を制御する機能を有する遺伝子産物(例、CLEC2)」などの知識の抽出が可能になった。ここで、その遺伝子産物がその生命現象を通して疾患を制御すると考えられることから、血栓塞栓症の関連遺伝子としてCLEC2など有力な疾患関連遺伝子候補の発見が可能になった。Gene Ontology、MeSH、ChEBIが提供する生物学的概念と遺伝子産物および化合物の関係情報を、線維素溶解ナレッジグラフに取り込んだ例では、血栓塞栓症関連遺伝子および化合物として100件以上の候補が発見された。生物学的概念オントロジー由来のナレッジグラフを対象に、SPARQL検索および、記述論理の手法を用いることで、直接的な関係は明示されていないものの、間接的に疾患に効果があることを示唆する物質(遺伝子産物、化合物)を効率的かつ正確に発見する可能性が示された。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p015 doi:10.18908/togo2018.p015 |
| 番 号 | 18 |
|---|---|
| タイトル | 希少疾患診断支援システムPubCaseFinderの社会実装を目指した取組み |
| 発表者 | 〇藤原豊史1)、山本泰智1)、金進東1)、高木利久2) |
| 所 属 | 1)情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター 2)東京大学 |
| 要 旨 | 患者の症状を入力するだけで、関連する希少疾患の候補を可能性が高い順に自動的にリストアップする、希少疾患診断支援システムPubCaseFinder(https://pubcasefinder.dbcls.jp)を紹介する。希少疾患データベースOrphanetに含まれる約4,000件の希少疾患を検索対象とし、疾患原因遺伝子を指定することで検索対象疾患を絞り込むことができる。また、各疾患には症例報告(文献)が紐付けられているので、利用者は疾患を検索するだけでなく、より具体的な過去の症例も合せて検索することが可能であり、診断の際にエビデンスとして活用できる。昨年以降のアップデートでは、利用者の要望をもとに、検索対象疾患の拡張、症状入力支援機能の改良、検索結果サマリ生成機能の追加などを行い、PubCaseFinderの社会実装を目指した改良を行った。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p018 doi:10.18908/togo2018.p018 |
| 番 号 | 19 |
|---|---|
| タイトル | Database of Pathogenic Variant(DPV)の開設 |
| 発表者 | 〇鈴木寿人、上原朋子、武内俊樹、小崎健次郎 |
| 所 属 | 慶應義塾大学 医学部臨床遺伝学センター |
| 要 旨 | 次世代シーケンサーの登場から数年を経て、網羅的遺伝子解析は以前よりも身近な診断手法になりつつある。網羅的遺伝子解析は解析者が遺伝子変異の影響を評価するために論文や遺伝子変異データベースでの報告等を参照し、検索を進める。データベースとして米国NIHが運営するClinVarが利用されることが多いが、ClinVarは欧米人から報告されたデータが多く、日本人の疾患関連遺伝子変異の登録件数は多くはない。 DPV(http://dpv.cmg.med.keio.ac.jp/dpv-pub/top)は日本人が執筆し公開されている論文から遺伝子変異についての情報を抽出し、頻度情報などのキュレーションを経て疾患関連の遺伝子変異として登録を行っている。特に希少疾患・難治性疾患の文献データを中心に収集しており、約2,000件の遺伝子変異の登録を行った。これらの変異はWEB上で検索することも可能であり、また各施設のパイプラインに組み込むためvcfファイルのダウンロードを行うこともできる。今後、AMEDが主導する「臨床ゲノム統合データベース事業」とも連携して登録データ数を増やす 予定である。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p019 doi:10.18908/togo2018.p019 |
| 番 号 | 20 |
|---|---|
| タイトル | 難病・希少疾患創薬データベース:DDrare |
| 発表者 | 〇坂手龍一1)、深川明子1)、水口賢司1)、鍵井英之2)、佐々木隆之2)、廣實万里子2)、森田正実2) |
| 所 属 | 1)医薬基盤・健康・栄養研究所 2)日本製薬工業協会 医薬産業政策研究所 |
| 要 旨 | DDrare(Database of Drug Development for Rare Diseases;難病・希少疾患創薬データベース)[1]は、厚生労働省の指定難病306疾患(平成28年)を対象として、臨床試験における開発薬物と、それらの標的遺伝子・パスウェイ情報を提供している。DDrareは、医薬基盤・健康・栄養研究所と医薬産業政策研究所との共同研究の成果として開発された[2, 3]。指定難病毎にClinicalTrials.gov(米国)及びJPRN(日本)より臨床試験情報を抽出し、関連する薬物情報(DrugBank)とも連結させた。それらの薬物情報に標的遺伝子・パスウェイ情報(KEGG)を対応づけることで、「疾患」、「薬物」、「標的遺伝子・パスウェイ」情報の相互参照を可能としている(平成30年7月現在、122疾患、328薬物、284遺伝子・108パスウェイ)。DDrareの開発は、創薬ターゲット選定や発症機序解明に資することを目的として進めている。 [1] DDrare:https://ddrare.nibiohn.go.jp [2]「 指定難病に対する臨床試験実施状況」政策研ニュースNo.48(2016.7) [3]「 指定難病のデータベース“DDrare”の紹介」同No.54(2018.7) |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p020 doi:10.18908/togo2018.p020 |
| 番 号 | 21 |
|---|---|
| タイトル | PubMedのTF-IDF解析による難病創薬プロファイルの抽出 |
| 発表者 | 〇平田誠、坂手龍一 |
| 所 属 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 難病資源研究室 |
| 要 旨 | 文章から重要語を抽出する際の特徴量として、TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency)がある。本研究ではPubMedから難病に関する要旨を取得し、薬物及び薬物と共起する名詞句を明らかにして、難病創薬のプロファイルを明らかにすることを目的としている。ここでは、難病研究資源バンク(https://raredis.nibiohn.go.jp)のHTLV-1関連脊髄症(HAM)と多系統萎縮症(MSA)を対象とし、これらを含むPubMedの要旨(2009年~;2018年8月取得)を構文解析して名詞句を切り出した。薬物(DrugBank)が含まれる要旨内の名詞句どうしの共起と出現頻度を数え上げ、TF-IDF値を掛け合わせたものを利用した。その結果、HAMで62薬物、MSAで119薬物の情報が得られ、疾患ごと及び年代ごとの情報が明らかとなった。“Mogamulizumab”-“anti-CCR4-antibody”など、有意な共起情報を網羅的に取得できた。これらの解析を進め、疾患横断的な難病創薬プロファイルとして活用していく計画である。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p021 doi:10.18908/togo2018.p021 |
| 番 号 | 22 |
|---|---|
| タイトル | 創薬・疾患研究のためのデータベース検索システム Sagace |
| 発表者 | 〇深川明子1)、長尾知生子1)、樋口千洋1)、五十嵐芳暢2)、森田瑞樹1), 3)、陳怡安1)、坂手龍一4)、 水口賢司1) |
| 所 属 | 1)医薬基盤・健康・栄養研究所 バイオインフォマティクスプロジェクト
2)医薬基盤・健康・栄養研究所 トキシコゲノミクス・インフォマティクスプロジェクト 3)岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科クリニカルバイオバンクネットワーキング事業化研究講座 4)医薬基盤・健康・栄養研究所 難病資源研究室 |
| 要 旨 | 医薬基盤・健康・栄養研究所では、JSTバイオサイエンスデータベースセンターと連携し、データベース横断検索システムSagace(http://sagace.nibiohn.go.jp)を開発・公開している。 Sagaceは、創薬・疾患研究に特化した約190のデータベースを選定・分類して検索対象とし、ファセット(データベースの分類)による検索結果の効率的な絞り込みと、メタデータ(エントリーIDや生物種、データベース名など)を反映した効果的な検索結果の表示を実装した検索システムで、一般的な横断検索システムよりも創薬・疾患研究に関する情報を効率的に発見できる。 Sagace独自に各製薬会社が公開している医薬品のインタビューフォームを検索対象に加えることで、薬理、薬物動態、毒性などの非臨床情報の検索機能を強化した。さらに内部処理の見直しを行っており、検索時間の短縮により、より効率的に創薬・疾患研究を支援する検索システムの構築を目指している。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p022 doi:10.18908/togo2018.p022 |
| 番 号 | 26 |
|---|---|
| タイトル | ナショナルバイオリソースプロジェクトの成果論文データベースの構築と活用 |
| 発表者 | 木村学1)、川島靖史1)、庄司健人1)、土屋里枝1)、萩原宏紀1)、渡辺拓貴1)、渡邉融1)、川本祥子2) |
| 所 属 | 1)日本ソフトウェアマネジメント(株) 2)情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所 |
| 要 旨 | ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)は、ライフサイエンス研究の基礎・基盤となるバイオリソース(動物、植物等)について収集・保存・提供などの整備を行っている。成果論文データベースRRC(https://rrc.nbrp.jp/)は、NBRPリソースを使用して行われた研究成果を集約したデータベースとして、リソースの価値を高めることに寄与している。研究成果のさらなる活用を目的に、今回データベースの改訂を行った。主に、インパクトファクターなどの新たなメタ情報・全体および生物種固有の統計情報の追加を行い、どんなリソースが成果に結びついているのか、どんな論文が注目されているのかを明らかにした。さらにデータベースに登録されたデータの利用を図るために、ディープラーニングを用いた解析を進め、論文の要旨を使って、リソースを作成した論文と、リソースを利用した論文の分類を試みたのでその結果を発表する。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p026 doi:10.18908/togo2018.p026 |
| 番 号 | 27 |
|---|---|
| タイトル | RujakBase; an integrated web resource for the omics database of Indonesian tropical fruits |
| 発表者 | 〇Deden Derajat Matra1)、 Arya Widura Ritonga2)、 Winarso Drajad Widodo1)、 Sobir2)、 Roedhy Poerwanto1) |
| 所 属 | 1) Crop Production Science Division, Department of Agronomy and Horticulture, Bogor Agricultural University (IPB)
2) Plant Breeding Division, Department of Agronomy and Horticulture, Bogor Agricultural University (IPB) |
| 要 旨 | Genetic resources of fruits native to Indonesia is the richest in the tropical region and has a great potential in the future utilization. The purpose of database is to collect, analyze, integrate genetics, genomics, transcriptomics, and metabolomics data to enhance more rapid research progress. The database can be accessed at http://www.rujakbase.id. All of the content includes organisms, sequence analysis, and publication were retrieved from public databases like NCBI and other reliable sources. Currently, the RujakBase manages 11 genera of Indonesian native fruits. |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p027 doi:10.18908/togo2018.p027 |
| 番 号 | 28 |
|---|---|
| タイトル | RAP-DB:イネアノテーションプロジェクトデータベース |
| 発表者 | 〇川原善浩1), 2)、岸川(広実)朋子2)、王暁輝1)、脇本泰暢3)、伊藤剛2) |
| 所 属 | 1)農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター 2)農業・食品産業技術総合研究機構 高度解析センター 3)ビッツ株式会社 |
| 要 旨 | イネは世界で最も重要な作物のひとつであり、2004年に作物では最も早くゲノム解読が完了した。そして、農業上重要な形質に関係する様々な遺伝子の単離や機能解析、DNAマーカー等を利用した分子育種等が精力的に進められている。このような研究において、ゲノム配列や遺伝子アノテーション情報はもっとも重要な基盤情報である。イネアノテーションプロジェクトデータベース(RAP-DB)は2006年よりイネのリファレンスゲノム配列やアノテーション情報の提供を開始し、10年以上が経った現在でも国内外の数多くの研究者から参照される基盤データベースとして利用されている。近年はOryzabase(NBRP、遺伝研)とも連携し、日々公表される学術論文を研究者が精査し、遺伝子構造や機能情報等の追加、修正を行う遺伝子情報
キュレーションに取り組み、最新のイネの遺伝子情報を提供するよう努めている。本発表では、RAP-DBが提供する遺伝子アノテーション情報や解析ツール、昨年より公開している300種以上のイネ品種のゲノム多様性情報を提供するブラウザについても紹介する。
RAP-DB: https://rapdb.dna.affrc.go.jp Sakai, H., et al., Plant & Cell Physiol., 54(2):e6 (2013) Kawahara, Y., et al., Rice, 6:4 (2013) |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p028 doi:10.18908/togo2018.p028 |
| 番 号 | 31 |
|---|---|
| タイトル | 植物ゲノム情報統合ポータルサイトPlant GARDENの構築 |
| 発表者 | 〇平川英樹1)、原田大士朗1)、Andrea Ghelfi1)、Jeffrey Fawcett1)、白澤沙知子1)、市原寿子2)、 中谷明弘2)、磯部祥子1)、田畑哲之1) |
| 所 属 | 1)かずさDNA研究所 2)大阪大学 大学院医学系研究科 |
| 要 旨 | 現在、モデル植物や実用作物など多種多様な植物のゲノム配列が解読されている。近年のシークエンシング技術の 進展により、今後、迅速にかつ高精度でゲノム配列が解読され、より多様な植物のゲノム配列が明らかになると考えられる。一方、様々な品種についてリシークエンスや転写産物の解読も行われており、品種間の塩基配列やゲノム構造の違いが調べられている。従来の統合化推進プログラムでは植物ゲノム統合ポータルサイトPGDBj(http://pgdbj.jp)を構築し、緑色植物40種とラン藻213種のオルソログ、65植物種約26万件のDNAマーカー、45種約1万6千件のQTL情報を公開した。第三期では、ゲノムワイドなデータに対応するようPGDBjの内容を一新し、新たにPlantGARDENを構築する。各植物で公開されているゲノムワイド多型情報をゲノムブラウザ上に集約させ、さらに、複数植物間での遺伝子配列の類似性に基づいたデータリンク基盤を構築することで、ゲノムを横断的に比較できるシステムを開発する。また、ユーザがNGSデータを投入しSNP解析を実施できるカスタム型多型・ハプロタイプ検出システムを構築している。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p031 doi:10.18908/togo2018.p031 |
| 番 号 | 35 |
|---|---|
| タイトル | 植物メタボロームデータの再解析・アノテーション高度化に向けた情報基盤整備 |
| 発表者 | 〇福島敦史1)、津川裕司1)、高橋みき子1)、小林紀郎2) |
| 所 属 | 1)理化学研究所 環境資源科学研究センター 2)理化学研究所 計算工学応用開発ユニット |
| 要 旨 | ライフサイエンスにおいて、データ測定方法の標準化と、データの再利用性確保とを目的とした枠組み整備は火急の課題である。メタボロミクスにおいては、ウェブ国際標準規格に沿ったRDF形式のメタデータ整備を含む生データの公開が未整備である。蓄積したデータの再解析や他データとの統合を通して、研究の再現、既存アノテーションツールの検証、データ測定の品質向上、機械学習精度向上ならびに新たな知見創出への貢献が期待される。 統合化推進プログラム「物質循環を考慮したメタボロミクス情報基盤」において、我々の研究グループでは、「植物データアノテーション高度化」を目指している。理研CSRSが保有するメタボローム測定データを精査して、理研メタデータベース(http://metadb.riken.jp/)から、さらには将来的に構築されるMassBank公共リポジトリから公開していく計画である。本発表では、データ再解析のための解析ソフトウェア開発[1]をはじめとした情報基盤整備の計画とこれまでの進捗について述べる。 [1]MS-DIAL(http://prime.psc.riken.jp/Metabolomics_Software/MS-DIAL/) |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p035 doi:10.18908/togo2018.p035 |
| 番 号 | 36 |
|---|---|
| タイトル | 物質循環を考慮したメタボロミクス情報基盤:KNApSAcK Family DB 生体活性DBの標準化とメタ代謝マップの構築に向けて |
| 発表者 | 〇金谷重彦、森田晶、小野直亮、江口遼平、Md. Altaf-Ul-Amin、黄銘 |
| 所 属 | 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学領域 |
| 要 旨 | オミクスと薬用/食用の知識を統合的に扱ったプラットフォームに従ってデータベースを構築すれば、社会の最重要課題である「健康」「医薬」を課題とした情報を体系的に検討できる。そこで、メタボローム研究を中心に薬用・植物知識ベース(機能性、配
合)、さらにヒト生理活性を統合的に扱うデータベースKNApSAcK Family DB(http://kanaya.naist.jp/KNApSAcK_Family/)[1]の構築を進めている。KNApSAcK Core Systemには、生物種と二次代謝物の関係データ情報が整理されており、現在までに、114,238種の生物種-二次代謝物の関係、二次代謝物の総数は51,086種となっている。また、白井ら(長浜バイオ大学)の開発した代謝物の三次元グラフマッチングアルゴリズム(COMPRIG)により、Twins DBにおいては二次代謝物間の類似性を検索することが可能になった。現在までに、生物種、二次代謝物にかかわる15種のデータベースの開発を進めている。構築されているKNApSAcK
family DBに物質循環を考慮したメタボロミクス情報基盤について、生体活性DBの標準化とメタ代謝マップをどのように統合するかについてプロトタイプDBを通してポスターにて発表する。
[1] Afendi FM et al., KNApSAcK family databases: integrated metabolite-plant species databases for multifaceted plant research, Plant Cell Physiol. 53, e1 (2012). [2] Saito M, Takemura N, Shirai T, Classification of ligand molecules in PDB with fast heuristics graph match algorithm COMPLIG. J. Mol. Biol. 424, 379-390 (2012) |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p036 doi:10.18908/togo2018.p036 |
| 番 号 | 39 |
|---|---|
| タイトル | jPOST統合環境の開発 |
| 発表者 | 〇奥田修二郎1)、渡辺由1)、守屋勇樹2)、河野信2)、松本雅記3)、高見知代3)、小林大樹4)、山ノ内祥訓5)、 荒木令江4)、吉沢明康6)、田畑剛6), 7)、岩崎未央7)、杉山直幸6)、田中聡8)、五斗進2)、石濱泰6) |
| 所 属 | 1)新潟大学 大学院医歯学総合研究科 2)情報・システム研究機構 ライフサイエンス統合データベースセンター 3)九州大学 生体防御医学研究所 4)熊本大学 大学院生命科学研究部 5)熊本大学 医学部附属病院 6)京都大学 大学院薬学研究科 7)京都大学 iPS細胞研究所 8)Trans-IT |
| 要 旨 | jPOST(https://jpostdb.org/)では、日本内外に散在している種々のプロテオームデータを統合し、統一された信頼基準で結果を解釈するために、(1)質量分析計から出力される生データを含む、プロテオームデータを投稿・蓄積するためのリポジトリ、(2)生データを再解析するための標準化されたワークフロー、(3)再解析後の高品質なプロテオームデータを蓄積・可視化するデータベースの3つを開発してきた。本年度から新たなプロジェクトとして、他のオミクス・データベースと連携し、シグナル伝達ネットワークや代謝ネットワーク等へのマッピングによって、生体分子による細胞機能、生命機能の解明に直接結びつくような解析ツールの開発を始めた。開発にあたっては、ゲノ ム変異情報を積極的に利用したプロテオゲノム解析や、腸内細菌叢などの多生物集団に対するメタプロテオーム解析から得られるデータも扱うとともに、メタボロミクス、グライコミクス等についてもその情報を取り込んだ解析を可能にすることを目標とし、幅広く生命科学研究者に利活用されるデータベースを構築する。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p039 doi:10.18908/togo2018.p039 |
| 番 号 | 41 |
|---|---|
| タイトル | 天然変性タンパク質データベース:IDEAL |
| 発表者 | 〇太田元規1)、嘉戸裕美子1)、坂本盛宇2)、細田和男3)、小池亮太郎1)、廣明秀一4)、福地佐斗志3) |
| 所 属 | 1)名古屋大学 大学院情報学研究科 2)(株)ホロニクス 3)前橋工科大学 工学部 4)名古屋大学 大学院創薬科学研究科 |
| 要 旨 | タンパク質の鎖の中で立体構造を形成しない部分を天然変性領域といい、天然変性領域を有するタンパク質を天然変性タンパク質という。天然変性タンパク質は、シグナル伝達・転写調節に関与するとともに、リン酸化といった翻訳後修飾部位を多く含み、タンパク質の機能に大きく関わっている。我々は天然変性タンパク質データベース:IDEAL(http://www.ideal.force.cs.is.nagoya-u.ac.jp/IDEAL/)を開発、運営している。IDEALでは、PDBのミッシング領域に加え機械的に収集する事が難しい実験的に確認された天然変性領域の情報を論文から収集している。また、天然変性領域中の相互作用部位をProSと呼び注釈付けしている。最近になり、天然変性部位のリン酸化に注目し、リン酸化を契機とする生物学的イベントの記述について検討を始めた。IDEALには2018年7月現在、913配列、9,004天然変性領域、559Prosが収録されており、天然変性タンパク質のデータベースとして世界最大の規模を誇っている。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p041 doi:10.18908/togo2018.p041 |
| 番 号 | 46 |
|---|---|
| タイトル | ヒト統合オーミクスデータベースDBKERO update 2018 |
| 発表者 | 鈴木穣 |
| 所 属 | 東京大学 大学院新領域創成科学研究科 |
| 要 旨 | 我々のグループで開発するデータベースDBKERO(http://kero.hgc.jp)では、ヒトゲノム多型・変異に生物学的機能注釈を与えるべく、臨床検体、培養細胞モデルの両面から多層オーミクスデータの統合を行っている。臨床検体データについては、今期、本データベースではCREST が終了するIHEC(国際エピゲノムコンソシアム)データの本邦での受け皿となるべく、日本チームの作成した正常肝臓、血管内皮、胎盤組織におけるエピゲノムカタログ(94検体からなるヒストン修飾、DNAメチル化、RNASeqの合計621データセット)を標準エピゲノムデータとして収載、ブラウズを可能とした。これに加えて東大徳永らの運営するヒトゲノム多型データベースとも融合し、HLA領域を含む多型情報さらに17 のGWAS解析より得られた日本人ゲノム多型を正常検体8,757検体、疾患検体6,816検体について公開した。 細胞モデルデータについては、約50種類のシングルセルデータ及びMinIONを用いて収集したヒトがんゲノムロングリードを公開した。また、これらのデータについて、統合オーミクス解析を可能とする一連のツール群についても公開を開始している。特に筆者らが今回公開した発現モジュール解析例について、肺腺癌細胞をモデルに詳解する。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p046 doi:10.18908/togo2018.p046 |
| 番 号 | 47 |
|---|---|
| タイトル | jMorp:日本人多層オミックス参照パネル |
| 発表者 | 〇田高周1), 2)、三枝大輔1), 2)、元池育子1), 2), 3)、井上仁1), 2)、青木裕一1), 2), 3)、 城田松之1), 2), 3)、植木優夫1)、牧野悟士1)、五丁千夏1)、小島要1), 2)、加賀谷祐輝3)、 小柴生造1), 2)、勝岡史城1), 2)、田宮元1)、清水厚志5)、山本雅之1), 2)、木下賢吾1), 3), 4) |
| 所 属 | 1)東北メディカル・メガバンク機構 2)東北大学 大学院医学系研究科 3)東北大学 大学院情報科学研究科
4)東北大学 加齢医学研究所 5)岩手医科大学 いわて東北メディカル・メガバンク機構 |
| 要 旨 | 東北メディカル・メガバンク機構(ToMMo)では東北メディカル・メガバンク事業における地域住民コホート調査に参加いただいた日本人5,093 人(男性433人、女性575人)の血漿サンプルの統合解析を行い、日本人集団における血漿中の代謝物の濃度分布やタンパク質の頻度分布を明らかにした。このような情報は疾患バイオマーカーの探索や、疾患予防や早期診断を行う際に有用な情報源になり得る。解析結果はjMorp(Japanese Multi Omics Reference Panel; https://jmorp.megabank.tohoku.ac.jp)にて公開している。2018年6月現在では、NMRで同定された37化合物の濃度分布、LC-MSで検出された257代謝物のピーク強度分布、加えて256タンパク質(男性190人、女性311人)の測定頻度を公開している。 また、メタボローム・プロテオーム情報にとどまらず、2018 年6月には日本人3,552人の全ゲノム解析から得られたアレル頻度情報をjMorpにて公開を始めた。これによりさらなる多層データ統合を推し進めてゆく。また、今後、解析サンプル数の増加や同定物質の種類を増加することでパネルの精度を目指し、また、ゲノム情報等との関連解析結果の増加を図ることでデータベースコンテンツの拡充を目指す。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p047 doi:10.18908/togo2018.p047 |
| 番 号 | 50 |
|---|---|
| タイトル | SCPortalen:一細胞データ再利用のためのデータベース |
| 発表者 | Imad Abugessaisa、野口修平、長谷川哲、Melissa Cardon、〇粕川雄也 |
| 所 属 | 理化学研究所 生命医科学研究センター |
| 要 旨 | 一細胞レベルでの遺伝子発現プロファイルをゲノムワイドに取得する技術の劇的な向上により、様々な細胞種の一細胞レベルでの遺伝子発現プロファイルデータが取得され、公共リポジトリ等で公開されている。これらのデータは取得した研究グループでの利用だけにとどまらず、その細胞を対象とした他の研究グループでの再利用も期待される。しかしながら、実験・データ解析手法の差異や、サンプル情報や実験条件などのいわゆる「メタデータ」の不足により、データの再利用には大きなハードルが存在する。そこで我々のグループでは、公開された一細胞遺伝子発現プロ
ファイルのメタデータを補正し、統一したデータ解析法を適用した結果をまとめたデータベースを作成し、公開している。本発表では、このSCPortalenデータベースについて紹介する。 http://single-cell.clst.riken.jp/ Abugessaisa, I et al., NAR (2018), https://doi.org/10.1093/nar/gkx949 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p050 doi:10.18908/togo2018.p050 |
| 番 号 | 51 |
|---|---|
| タイトル | The FANTOM web resource, update 2018 |
| 発表者 | 〇野口修平、Marina Lizio、Imad Abugessaisa、Jessica Severin、粕川雄也、川路英哉 |
| 所 属 | 理化学研究所 生命医科学研究センター |
| 要 旨 | 哺乳類ゲノムの機能アノテーションを目的とした国際共同研究FANTOM(Functional ANnoTation Of Mammalian Genome)プロジェクトの第五回目であるFANTOM5では、ヒトやマウスなどの様々な初代培養細胞や臓器、細胞株、時系列サンプルより構成される約3,000サンプルを対象に、転写開始の頻度を一塩基単位でゲノムワイドに測定した。本測定データを元にヒトゲノムの機能領域として重要な役割を果たすプロモーター、エンハンサー、そして非コードRNAのアトラス(地図)を作成し、得られたデータや解析結果についてはデータアーカイブ、そして複数のデータベースに格納され、多様な側面からの利用に供されている(http://fantom.gsc.riken.jp/5/)。 今回のアップデートではdog、rat、chicken、macaqueのCAGE(Cap Analysis of Gene Expression)データ、および、それを用いた解析により同定したプロモーター領域のデータを追加した。これらのデータはFANTOM5のヒトやマウスのデータと同様に利用可能である。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p051 doi:10.18908/togo2018.p051 |
| 番 号 | 52 |
|---|---|
| タイトル | SSBD:細胞・発生画像情報と生命動態情報の統合データベース |
| 発表者 | 〇京田耕司1)、遠里由佳子1), 2)、ホーケネス1)、糸賀裕弥1)、大浪修一1) |
| 所 属 | 1)理化学研究所 生命機能科学研究センター 2)大阪電気通信大学 情報通信工学部 |
| 要 旨 | SSBD(Systems Science of Biological Dynamicsデータベース)は、生細胞イメージングにより得られる生命現象に対する画像データや画像処理により得られる定量データを共有するデータベースである(Tohsato et al. 2016; http://ssbd.qbic.riken.jp)。現在、多種多様な生命現象に対する610セットの画像データ、480セットの定量データを公開している。画像データはオリジナルフォーマット、定量データは我々が開発した統合フォーマットBDML/BD5で提供しており(Kyoda et al. 2015)、加えてREST APIによる両データへのアクセスも可能である。昨年度より、細胞・発生生物学分野のデータの統合を目指し、日本細胞生物学会、日本発生生物学会およびABiSとの連携を開始した。また、国際的なデータ共有の仕組みを構築するために、英国のOMEプロジェクトや欧州のEuro-bioimagingプロジェクトとの連携を開始した。本年度より、画像・定量データから統計解析等により得られる解析結果を共有するシステムを開発している。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p052 doi:10.18908/togo2018.p052 |
| 番 号 | 58 |
|---|---|
| タイトル | MicrobeDB.jp ポータル:統合微生物データベースのポータルサイト構築 |
| 発表者 | 〇藤澤貴智1)、森宙史1)、谷澤靖洋1)、神沼英里1)、内山郁夫2)、山田拓司3)、高橋弘喜4)、中村保一1)、 黒川顕1) |
| 所 属 | 1)情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所生命情報研究センター 2)自然科学研究機構 基礎生物学研究所理論生物学領域 3)東京工業大学 4)千葉大学 真菌医学研究センター |
| 要 旨 | 我々は、微生物に関するデータを系統・遺伝子・環境の3つの軸に沿って整理・統合した統合微生物データベースMicrobeDB.jp(http://microbedb.jp/)を公開している。現在、公開されている約17万サンプルのメタゲノムデータ、約1万7千株のゲノム・ドラフトゲノムデータを収録し、微生物のゲノムやメタゲノム情報を容易に利活用するために継続的な開発を行っている。収録データについては、微生物ゲノム情報を記述するためのオントロジーを整備し、RDF形式でデータセットを記述し、さらには、解析プロトコルの標準化および解析パイプラインの開発および連携を実施してきた。本発表では、データベースのユーザビリティ向上を目的として、ユーザインターフェース改良とユーザのゲノム・メタゲノムを解析するためのレポジトリ機能を統合したMicrobeDB.jpポータルサイトを構築した。また、環境情報、宿主生物、温度、pHなどのメタデータによるファセット検索から解析済みのメタゲノム解析データを比較する機能の提供を開始した。さらに、データ更新に関わるサンプルメタデータ記述RDFの更新および メタデータのキュレーションについても発表する。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p058 doi:10.18908/togo2018.p058 |
| 番 号 | 62 |
|---|---|
| タイトル | 健全にする生態システム制御機能(湖沼池の免疫)の扉を開く鍵 |
| 発表者 | 長正一郎 |
| 所 属 | 有限会社アクアラボ |
| 要 旨 | 湖沼池の藻類汚濁を健全に改善する生態システム制御機能させる、鍵の紙を分解するセルロース分解酵素を持つ菌類が堆積層にいる、その仲間の菌類群集の産する酵素に含まれるブドウ糖(グルコース)が活動源(エネルギー創出)となって、一旦細菌
群集や原生生物各種が増殖した後休眠胞子なるか枯死して沈降して堆積層に摂取したリンを閉じ込める、リンは窒素や炭素と違って大気と交換しない性質でリンを制限して抑制する、鍵が健全にする生態システム制御機能(湖沼池の免疫・生態系機能)の扉を開き、 藻類汚濁の抑制現象に導く。 これらの常時観測は、水温と溶存酸素(DO)は水質計測計器の飽和溶存酸素(Saturated DO)を算出機能付きでDOとSaturated DOの差を得て生態系生物圏を、同時にフローイングインジェクションとイオンクロマトで水質を、ITで観測値収集AIで生態系機能様式の蓄積と情報活用(データベース)する。 合わせて随時観測として、生態系生物圏の変化とらえる、フローサイトメトリーの形態別定量と次世代シーケンス遺伝子解析の種の同定と定量の計測と検定の情報により、ITで観測値収集AIで生態系機能様式の蓄積を情報化(データベース)する。 生態系機能蓄積情報(データベース)とする。 参考HP http://researchmap.jp/chou 参考文献 用水と廃水 Vol.60 No.9 603~610 2018 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p062 doi:10.18908/togo2018.p062 |
| 番 号 | 63 |
|---|---|
| タイトル | 微生物の安全な利用に向けたNITEの情報提供の取り組み |
| 発表者 | 〇黄地祥子、藤田真澄、桑田祐輔、木村明音、牧山葉子、山本美佳、
北橋優子、宮澤せいは、市川夏子、川﨑浩子、 加藤愼一郎 |
| 所 属 | 製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター |
| 要 旨 | NITEバイオテクノロジーセンターでは、微生物の安全かつ適切な利用の支援を目的として、2つのデータベース
「微生物有害情報リスト(平成26年公開)(https://www.nite.go.jp/nbrc/list/risk/)」と「MiFuP Safety(平成29年公開)(http://www.bio.nite.go.jp/mifup_safety/)」を公開している。
「微生物有害情報リスト」は、微生物(細菌、真菌)の危険度/有害性の判断基準となる国内外の情報を一元化したものであり、各微生物のバイオセーフティーレベル(BSL)分類や国内法規制の適用の有無などの情報を、学名(旧名、異名を含む)から検索することが可能である。 一方、「MiFuP Safety」は、微生物(細菌)のゲノム情報から有害性機能に関わる遺伝子を検出し、微生物の有害性機能(毒素産生能、薬剤耐性等)を推定するデータベースである。本DBには、有害性機能に関与する遺伝子の組合せの情報及びそれら遺伝子のオーソログの検出条件(配列相同性やモチーフ・ドメインの有無)が搭載されており、ユーザーのゲノム配列情報(塩基配列又はアミノ酸配列)から有害性機能の発揮に必要な遺伝子を自動検出し、有害性機能を推定することが可能である。 本発表では両データベースの概要と共に、今後開発を予定している、両データベースの統合サイトについて紹介する。 |
| 発表資料 |  doi:10.18908/togo2018.p063 doi:10.18908/togo2018.p063 |
ポスター発表参加者募集!(受付終了)
シンポジウムの一環として、ポスター発表を開催します。生命科学分野のデータベースを様々な形で研究に利活用しているユーザの方々、生命科学分野に限らずデータベースの開発や運用に携わる方々にご発表いただき、シンポジウム参加者とデータベースについて幅広く議論していただければと考え、ポスター発表参加者を下記募集要領のとおり広く募集いたします。特に、ユーザから活用例をご紹介いただくことは、データベースの利活用を促進し、また、今後のデータベースの開発・運用にとっても大変参考になると考えます。多くの方からの応募をお待ちしています。
ポスター発表募集要領
内容例 : 1次データベースの構築・運用
複数のデータベース組み合わせ等の2次データベースの構築・運用
データベースを利用したツール開発(解析、可視化等)
データベース利用による研究の効率化
応募締切: 2018年7月20日(金)12:00まで
応募方法: 受付は終了しました。
以下必要事項について留意事項を確認の上、申込フォームからお申し込み下さい。
発表タイトル
発表要旨(参考文献も含め500文字程度)
発表者(連名者含む)情報
留意事項: ・展示スペースに限りがあるため、応募者多数の場合は選考を実施いたします。
採択の可否については、7月末日までに発表者のメールアドレス宛に連絡いたします。
・ご応募の中から、口頭発表(15分程度)をお願いすることがあります。こちらも7月末日までに連絡いたします。
・ポスターセッションは午後に予定しております(45分程度)。
・ポスターセッションの直前に、ライトニングトーク(1ポスター1分での簡単な発表内容の紹介)を実施いたします。
なお、ライトニングトークの様子は、当日インターネットでライブ配信する予定です。
・ポスター発表の氏名・所属・タイトルおよび要旨は、事前にシンポジウムウェブサイトから公開するほか、
要旨集として当日配布する予定です。
・当日発表いただいたポスターは、後日データを提出いただき、PDFを同サイトから公開する予定です。
なお、ポスターには、DOI*1を付与します。また、データベース統合化の趣旨に鑑みて、
公開に際してのライセンスの扱いはCC-BY*2とし、公開サイトにその旨を記載する予定です。
*1 DOIは、Digital Object Identifierの略で、デジタルコンテンツに付与される国際的な識別子です。DOIは容易にURLに変換することができます。このURLは、コンテンツ本来のURLにリダイレクトされます。一度登録されたDOIは変更されません。このため、コンテンツ自体のURLが変更されても、コンテンツのDOIを知っていればリンク切れすることなくアクセスすることができます。詳細は、日本で唯一のDOI登録機関であるジャパンリンクセンターのウェブサイトをご参照ください。
*2 CC-BY![]() は、国際的非営利組織クリエイティブ・コモンズが提唱するライセンス形態のひとつで、「クレジットを表示すること」を条件に著作物の利用を許可するというものです。詳細は、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンの解説サイトをご参照ください。
は、国際的非営利組織クリエイティブ・コモンズが提唱するライセンス形態のひとつで、「クレジットを表示すること」を条件に著作物の利用を許可するというものです。詳細は、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンの解説サイトをご参照ください。